
書籍『FRAGMENT UNIVERSITY 藤原ヒロシの特殊講義 非言語マーケティング』の発売に伴い、カルティエ協賛によるFRAGMENT UNIVERSITYの特別講義が開催。そのダイジェスト版として、HF流の「ネーミング論」をお届けする。
2月26日に発売された書籍は、2023年の10月より約半年間にわたって開催されたFRAGMENT UNIVERSITY全8回の講義録。今回は、2月26日に開催されたカルティエのサポートによる「ネーミング論」と題した90分の特別講義の様子をレポート。約300人のオーディエンスが集まった。

講義は東京都港区・赤坂の草月会館内にある草月ホールにて行われた。来場者には特典として、HFのサイン入り書籍および、特別に制作されたFRAGMENT UNIVERSITYの刻印入りのモレスキンのノートブック(非売品)が配られた。オンライン配信はなし、フィジカルのみの特別な空間づくりも、HFが常に大切にしていることの一つ。
カルチャーの語源は“耕す” 無駄と余白がHFの本質
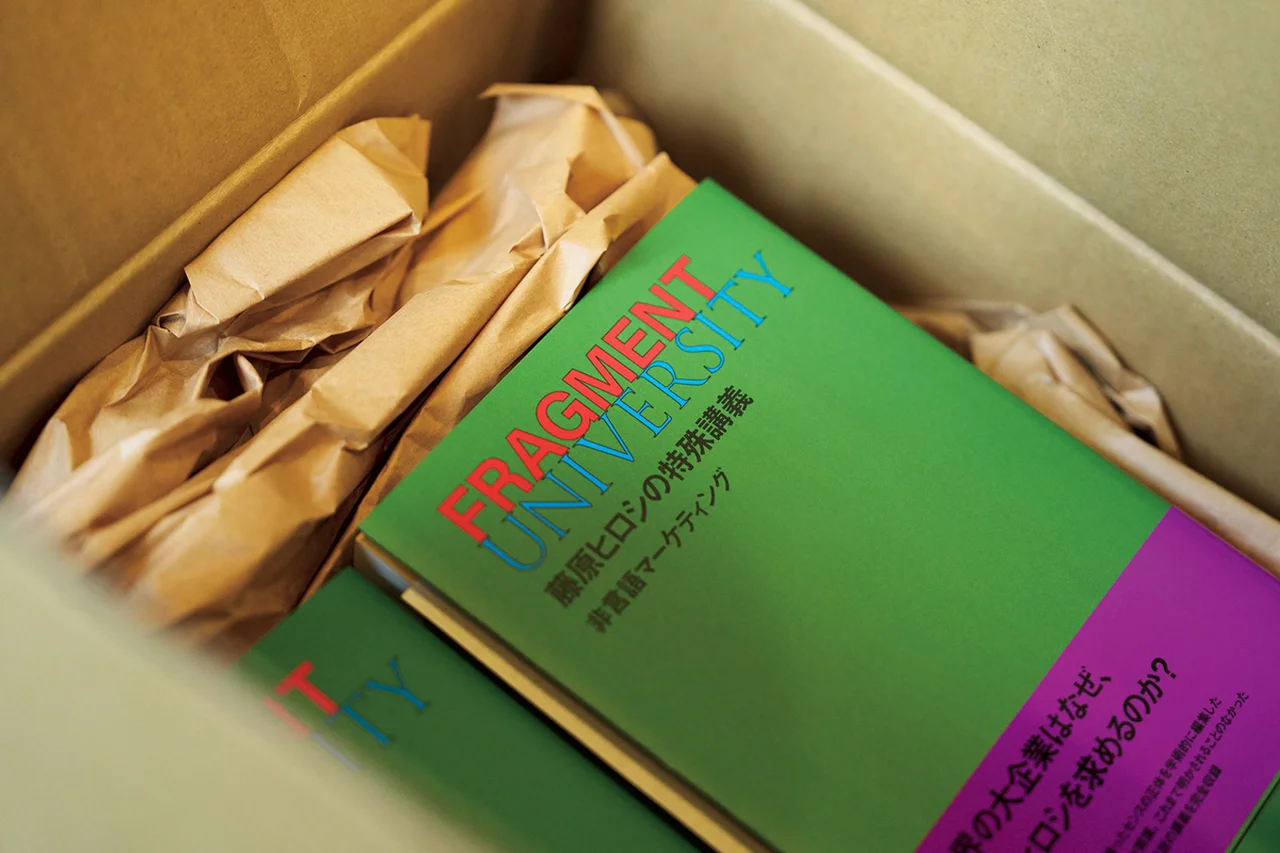

藤原:2023年の夏に東大のオープンキャンパスに来ていた方は覚えているかと思いますが、カルチャーの話をおさらいしたいと思います。カルチャーってすごく大切なことなんですけど、辞書で調べると「文化」と出るし、僕も「一体なんだろう?」ってずっと気になっていました。
約1000万年以上前、まだ猿しかいなかった時代はもちろん言語もなく、チンパンジーが陸に下りる前は、樹上で果物を食べながら生活していたと言います。しかしその何百年か後に自然環境の変化で地殻変動が起きて、砂漠化したらしいんですね。それまでは、ナックルウォークという、手の指を折り曲げて四足歩行をしていたチンパンジーが、森の中から地上に下りて生活をし始めて、二足歩行になった。この進化がラミダス猿人と言われています。砂漠化したことで木の茂った森が遠くにある状況になり、食べ物を求めて転々と動き回らなければならなくなった。でも、二足歩行のラミダス猿人は両手が使えるので、森に行って果物をとって、自分の家族のもとに持って帰れるようになった。それが理由で彼らが生き残り、ラミダス猿人がホモ・サピエンスの先祖になったと言われています。

学校で習った人もいるかもしれないですけど、1974年に「ルーシー」という猿人の化石が発見されると、顎の骨格とかで、この頃から肉食になったとか、いろいろわかってきたらしいんですね。草食動物は起きている間はずっと食べていないと栄養が足りないらしく、一日中食べ物を探して生活していたっぽい。それが肉食になったことで栄養が行き渡り、時間ができた。そして無駄なことを考えるようになって、脳が活性化して、人への進化が始まっていったということです。これは僕の想像ですが、果物とかお米を食べるようになると、種を植えるときに、どうしたらもっとおいしくできるか?と考えるようになったと思うんですよ。
それで、耕すんです。この耕すというのをラテン語で〝コレレ”と言います。これがカルチャーの語源です。みんなが知ってるカルチャー=文化じゃなくて、カルチャーは「心を耕すもの」なんじゃないかということに僕は行き着きました。それは時に非合理的であったり非実用的です。例えばフリースのパンツみたいに心地よくて、あったかくて、気持ちがいい。そういうものも素晴らしい。でも、ボンデージパンツのようにジッパーやひもがついていてもいいんじゃないか。無駄を加えることで面白くなり、自分自身も楽しくなる。人を魅了することが心を耕すことであり、カルチャーの本質じゃないかなと思います。
この非言語マーケティングという講義の内容は、もしかしたらマーケティングにもカルチャーがあるんじゃないか、という仮説に基づいて考えてきました。僕がずっと洋服を作ったり音楽をかけてきたことは、この遊びや無駄を大切にしてきたことが大きかったんじゃないかなと思います。
マーケティングの世界では「わかりやすさ」が正しい

藤原:さて、今回の講義はカルティエさんのスポンサードで、こんなにいい会場でやらせてもらっています。で、なにか面白い話を、と考えてきました。では、准教授の皆川(壮一郎)くんを呼びたいと思います。
皆川:よろしくお願いします。
藤原:物にはいろいろ名前がつけられますよね。皆川くんは元博報堂の社員ですが、広告代理店の方々やコピーライターが、一生懸命名前を考えるんですよね。
皆川:はい、今もやっています。
藤原:では、いいネーミングとはなんでしょう。これらがいいネーミングとされているものの代表らしいです。
皆川:ChatGPTにいいネーミングの例を聞いたら、この3つが出てきました。説明するまでもないですよね。理由は名は体を表してるからです。例えば「ポッキー」は食べる時に“ポッキン”という音がすることに由来しています。「カップヌードル」は初めてのカップに入ったヌードルであり、「甘栗むいちゃいました」は日本人なら誰でも意味が通じる名前かと。
藤原:とにかく「わかりやすいもの」がマーケティングの世界ではいいネーミングとされているってことですよね。
皆川:そうですね。メーカーの人や、広告会社の人は日夜商品名を考えていて。その多くは多数決で決められたりとか、あとは100も案を出したりとか。そういうマーケティングの世界の基準で、ネーミングは考えられている。こういう世界もあるんですよ、と以前にヒロシさんにお伝えしたことがあります。
藤原:医薬品などはわかりやすいネーミングがいいのは多少理解できますが、それにしてもっていうのもありますね。発毛で「ハツモール」、無臭で「ムシューダ」とかね。これが一般的にはいいネーミングとされている。
皆川:そのとおりです。しかも売れている商品ならなおさら。「ムシューダ」のことをほとんどの日本人が知っていますし。
藤原:タクシーに乗る人は、「KINUJO」わかりますよね。絹のような髪の女性になるドライヤー。CM、なんでしたっけ。「パリコレでも使われ〜」。
皆川:SNSで物議を醸してました。「パリコレ」という名称はないんでしたっけ?
藤原:あるんですけど、正確には「パリ・ファッション・ウィーク」ですよね。それと同じで、前にちょっと話題になった、おじさんのパーカ問題。あれ、若者はみんなパーカのことフーディって言うから、パーカって言ってる時点でおじさんじゃないかと思いました。
日本のネーミングは「ネタバレ」文化
皆川:無駄な時間を大事にしているフラ大は、逆ネーミングがあるとか、くだらない話題でいつも盛り上がっています。
藤原:僕がもし総理大臣になったら、いちばん最初に「皿うどん」と「ちゃんぽん」を逆に変えます。どちらかというと、ちゃんぽんのほうが麺が太くて、うどんっぽくて、皿うどんはまったくうどんに見えない。あんかけベビースターラーメンじゃないですか。
皆川:やや独断と偏見が入ってますが、ヒロシ教授がこれだけは言っておきたいっていうのは、洋画タイトルの邦題への改変について。豊作だったので選りすぐりだけ紹介します。
藤原:例えば『FROZEN』。これ、タイトルだけでなんとなく内容を想像するのが面白いのに、邦題になると『アナと雪の女王』と最初に説明してしまうんです。もう一ついきましょう。数年前の韓国映画『パラサイト』ですね。アメリカで公開されたときのパッケージと違って、日本版は『半地下の家族』とサブタイトルがつくんです。これもタイトルでネタばらししちゃっている。
皆川:でも、すごいヒット作でした。
藤原:わかりやすく説明をつけるというのが日本の文化の始まりかもしれないですね。
皆川:では、映画以外の事例も。
藤原:これが僕は本当に、日本のネーミング文化の象徴だと思うんです。『The Emperor’s New Clothes』。『裸の王様』です。原題は『王様の新しい服』という含みをもたせたタイトルなのに、日本では最初からオチを言ってしまい、表紙にまで王様の裸姿を描いてしまう。面白いところを先に見せて注目を集める、ということですよね。『裸の王様』はすごく古い物語だと思うので、わかりやすさを大事にする日本の文化は、かなり昔から始まっていたんだと思いました。
皆川:毎回、打ち合わせ時にスライドの資料を作成するのですが、ヒロシ教授は常にネタばらしはやめよう、余白を残そう、ってよく言います。この講義に携わった約2年っていうのは、僕が広告の人間として歩んできた道と、本当に真逆でした。僕が習ってきたいいネーミングとは、とにかくシンプルで発音しやすい。意味やイメージが重要。そして10年後も愛されるネーミングにしようみたいな感じで、ずっとやってきました。
藤原:でも奥行きがあり、余白が残っていると、一体これってどういう意味なんだろうって調べたくなる。なるほどこういうことか、と思ったものは、心に残って、覚えていられるものじゃないかと思います。
無駄や遊び心のあるネーミングとは
皆川:そこで一般論に対して、ネーミングにこそ、無駄や遊び心を入れたほうがいいんじゃないか、と考えました。
藤原:まずはポルシェの「カイエン」。みんな知ってるクルマだと思うんですが、その意味を知らない人も多いのでは。
皆川:どういう意味なんでしょう。
藤原:香辛料の「カイエンペッパー」から取っているんです。普通、クルマに胡椒とか唐辛子みたいな名前って、なかなかつけないじゃないですか。例えば「スピードスター」って名前はイメージどおりですけど「カイエン」というのは結構面白いネーミングだなと。
皆川:僕が担当者なら、ハイスペックであること、SUVなのにスピードが出るみたいな特徴が言えてないなって、考えてしまいます。
藤原:それが採用されて、結果的にはポルシェの中でもカイエンという名前が独り歩きしているのは、面白いなと思いますね。次はロールス・ロイス。「カリナン」って、世界でいちばん大きい(当時)と言われるダイヤモンドの名前なんです。621グラムなんで、ペットボトルぐらいの重さですね。でも急に名前を「あ、カリナンにしよう」としても多分できないと思うんですよ。
皆川:商標権とか大変ですもんね。
藤原:おそらくロールス・ロイスはもう何年、何十年も前からカリナンっていう名前をいつか使おうと取得していたんじゃないか。
皆川:そして温めていた。
藤原:はい。そういうところも含めて、やっぱりいいネーミングだなと。

藤原:さて、カルティエには「タンク」という時計があります。どうして時計にタンク?って思うじゃないですか。
皆川:小さいですし。
藤原:これもネーミングの妙の一つ。戦車はカクカクしてるっていうかね、なかなか時計と結びつかないですよね。
皆川:戦車は第一次世界大戦のときに初めて使用されて、戦争を収束させた立役者と言われていて。僕が聞いた話ではタンクはコンコルドのような、「夢の乗り物」みたいなテンションだったらしいんです。
藤原:戦争の象徴というよりも、戦争を終わらせたピースメーカー的な存在だった。
皆川:そして100年後になって、「タンク」がカルティエの代表的な時計になっている。
藤原:例えばロールス・ロイスが「タンク」とか、カルティエが「カリナン」と名づけても当たり前ですよね。やっぱり逆ネーミングだったことがよかったのでは、と思います。
皆川:ロールス・ロイスに「タンク」ってありそうですもんね。
藤原:でも、なんか面白くないというか、虫コナーズ的なことになるんですか。
皆川:虫コナーズもいいネーミングですけど、直球でわかりやすさ重視ですよね。
藤原:はい。そこがネーミングの面白いところというか。僕らも何か名前をつけるなら、ひねりが必要なところかなと。
皆川:カルティエって、1847年にパリで創業され、王族や著名人が愛用してきた歴史が今の地位を築いているのはご存じのとおりです。でもこの講義でかかわるようになって、カルティエの意外な一面を学びました。
藤原:高級なイメージなのに、タンクっていうのは、面白いところですよね。
皆川:すごくエレガントなデザインなのに、戦車をモチーフにして作られている。実は、僕にとってまったく縁がないブランドだと半年前まで思っていたんですけど。身近に感じたのは、ヒロシ教授がつけていたタンクです。
藤原:カルティエってファインジュエリーのブランドだし、時計もドレスウォッチがメインなので、自分とはあまり縁がないと思っていたけど、この黒いタンクは欲しくなりました。シンプルで真っ黒な文字盤に、NATOベルトをつけたら面白いかなと思って。
皆川:今日はネーミングを考察する講義なので、ほかにもカルティエのことをいろいろ調べました。「ベニュワール」という時計の名前の由来を教えてもらったんですが、通称だったものが後から公式名称になったそうです。ベニュワールはフランス語で「バスタブ」という意味とのこと。
藤原:もともとの名前は「オーバル」でした。
皆川:楕円形のケースがバスタブみたいだということから公式名称になったという話もあるし、オペラ座のボックスシートがバスタブ型だったことが由来という説もあったり。とにかくエピソードの一つ一つが知的でユーモアがあって。諸説が飛び交うっていうのは、いいブランドの証拠だと思いませんか?
藤原:急にそんなこと言われても僕にはわからないですが(笑)。
皆川:ヒロシさんが以前つけていた「ジュスト アン クル」も、パンクっぽいデザインだなと気になってネーミングの意味を調べたら、「ただの釘」っていう。’70年代に発売されたんですが、時代背景をすごく反映したものだったんです。世の中がヒッピーカルチャー一色で、反骨精神にあふれかえっていた時代に、日用品の釘をモチーフにジュエリーを作ったらいいんじゃないか、ということでできたらしいです。
藤原:僕が買ったのは’70年代じゃなくて、再販されたときですけどね。ネーミングだけじゃなく、物そのものが面白いというか。
皆川:カルティエには、なぜこういった事例が多いのか調べると、創業者の孫であるルイ・カルティエが1898年に経営に加わってからの影響が大きかった。ルイの次弟のピエール・カルティエがロンドンに拠点を構えた後、ニューヨークに支店をオープンさせた。で、末弟のジャック・カルティエがロンドンの経営を継承したそうです。本社と支社ってよくある話ですが、メールもファクスもない時代に、お互いがどうクリエイションし合っていたのか。それぞれの国で生まれた時計を調べてみると形、商品の血筋こそ違うものの、すべて上品なんですよね。
藤原:きっとラグジュアリーみたいなものが根底にあるからそれがベーシックになるんです。だからこうやって過激なことをやったり、冒険ができるんだと思います。
皆川:偶然や成り行きの中でネーミングが生まれ、諸説が後からついてストーリーがつくられていく。とても器の大きいブランドだと感じました。あと、「クラッシュ」っていう時計があって、これは見たことがある人も多いんじゃないでしょうか。
藤原:すごく人気ですよね。
皆川:これは自動車事故に遭って形が変わってしまったオーナーの時計をモチーフにしたんじゃないかという逸話がネットで調べると出てきます。一般的にブランディングって、ブレが許されない、一本筋が通っているものが正しいとされている一方で、カルティエはこんなに遊びや余白が多いブランドなんだっていう印象を受けました。
藤原:何事もやっぱり余白を残して、みんなで考えるのが大切というか。それこそスマホがなかった時代は、一枚の写真から情報を得るために、そこに隠されたいろいろな無駄について考えていた。それが楽しかったんだと思います。
皆川:遊びと無駄を追いかけてきたフラ大の考え方にも近いものがあるということですね。今日はどうもありがとうございました。
FRAGMENT UNIVERSITY 藤原ヒロシの特殊講義 非言語マーケティング
藤原ヒロシ著 / ¥2,200(税込)
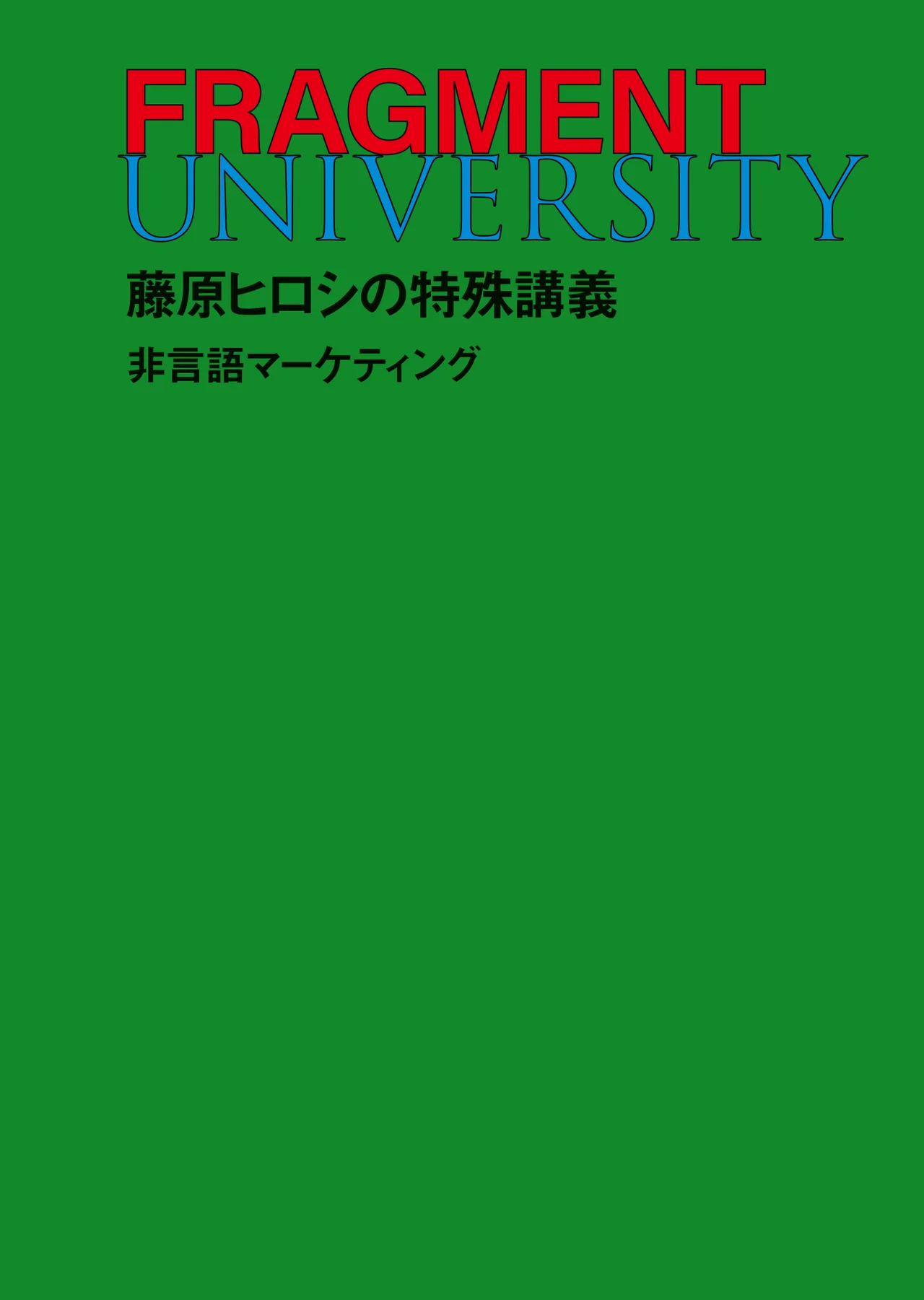
2023年10月から2024年3月まで開講された 「藤原ヒロシの特殊講義 非言語マーケティング」の内容を再編集した講義録。90年代に「裏原宿」というカルチャーを築いた後はファッションの枠を超えて支持され、 ナイキ、ポケモン、スターバックス、ルイ・ヴィトンといった世界的な企業から常に求められ続けている HF流のアイデアの作り方や育て方、 コラボレーションに対する姿勢やコミュニケーションのスタイルを分析した、すべてのビジネスパーソン必読の一冊。
ファッション・デザイナー、ミュージシャン、音楽プロデューサー、大学教授などいろいろ。
















